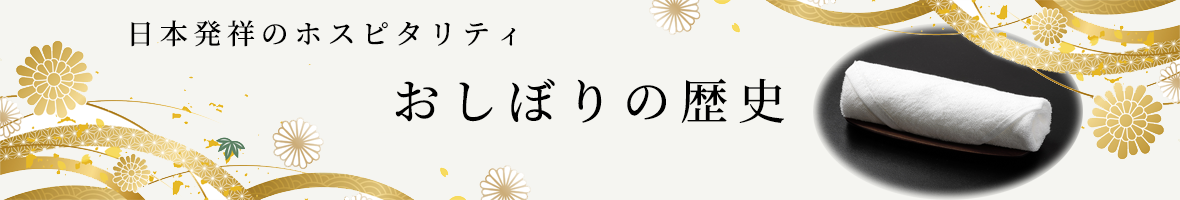
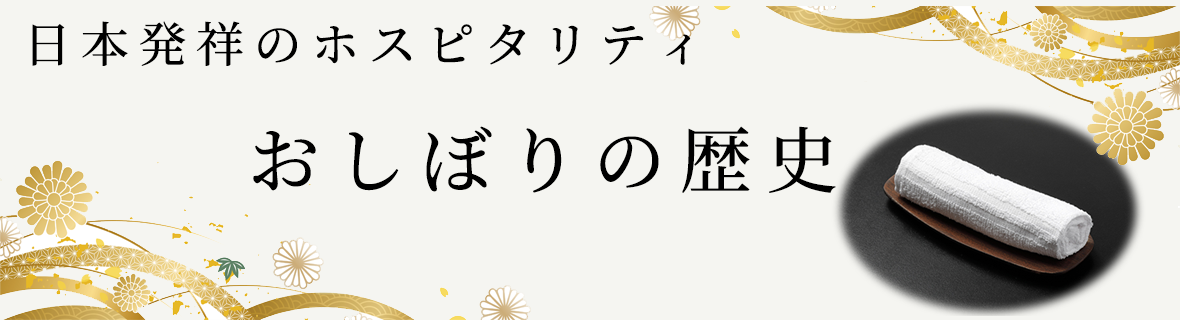

日本発祥のおしぼりは、古くは『古事記』や『源氏物語』が書かれた時代まで遡ると考えられており、お公家さんが客人を家に招く際に提供した、“濡れた布”がその前身となっているよう です。
江戸時代になると、木綿の手ぬぐいが普及したことで、旅籠(はたご)と呼ばれた宿屋の玄関には旅人のために水を張った桶と手ぬぐいが用意されるようになり、客はその手ぬぐいを桶の水に浸してしぼり、汚れた手や足をぬぐいました。
この“しぼる”という行為が「おしぼり」の語源と言われています。



戦後復興で日本に少しずつ飲食店が増えていくと、戦時中の混乱で消えかけていたおしぼりの習慣が徐々に普及し始めます。
当時はおしぼりを自店で洗い、丸めて自家製のおしぼりをつくり提供していましたが、客数が増えると手作業では追いつかなくなり、“おしぼりを貸す”ビジネスが生まれました。最初は自家製の洗濯機を使い、1本1本手で巻いて飲食店などに卸していましたが、その後外食産業がさらに発展したことで業者は量産体制を整えるまでになり、貸しおしぼり業が一つの立派なビジネスとして確立されるようになったわけです。

おしぼりのサービスは、他の産業にも普及します。1959年より日本航空は国際線で離陸前の搭乗客におしぼりを提供し始め、このサービスが好評で、日本以外の航空会社でも国際線でおしぼ りを出すようになりました。
また、海外の雑誌にも取り上げられるほど、日本以外の各国に普及し始めています。中国では比較的普及が早く、高級料理店ではおしぼりが登場することも少なくありません。
ナプキンを使用する習慣がある欧米圏でも、日本からおしぼりのローリング・包装を自動的に行う機械を導入し、サービスの提供を行っている企業があります。
